業務効率を落とさずに帳簿や書類を電子化できましたでしょうか?
「電子帳簿保存法の改定に対応せよ」今回は、電子帳簿保存法にどう対応していくかを考えるのに役立つ資料をご紹介します。
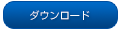
3. 対応方針と範囲を固めましょう電子帳簿保存法は、国税関係の帳簿や書類の保存に系る負担を軽減するための法律です。
ペーパーレス化することで、業務改善やコスト削減ができるという前提になっています。
ですが成立当初は、法律適用の為の要件が多く、電子化に積極的な企業は多くありませんでした。
数回にわたって改正が行われ、昨年度の改正で大幅に緩和されたので、電子化を進める企業が増えてきました。
確かに、電子データをわざわざ印刷して紙で保存していたものがデータ保存で済むのならコスト削減になるでしょう。
しかし、対応することによって業務に支障はでていませんか?
今までの業務フローを変更するには何かしらの手間や混乱を招きかねません。
全ての帳簿や書類を今すぐ電子化しなければならないものではありません。
御社の状況や業務フローを考慮して、どこまで対応するのか考えていきましょう。
「電子データを保存して保管する」にあたって、最低限必要なものは「保存場所」です。
光ディスク、HDD、SSD、社内のファイルサーバ、クラウド…保存方法は色々あり、どれも一長一短です。
◆光ディスク(DVDやBlu-ray)
水、静電気、衝撃に強く、追記型に保存すればデータ改ざんを行えないという特性を持っていますが、1枚1枚の容量が少なく、検索機能に劣ります。
◆HDD
記憶容量が大きく、安価で長期保存に適していますが、衝撃や熱に弱く消費電力が多いです。
◆SSD
衝撃や熱に強く、読み取り速度が速いですが、価格が高く、寿命が短く長期保存に向いていません。
◆社内ファイルサーバ
社内のファイルサーバに保存すれば、特に用意するものはありませんが、複数人がアクセスし普段使用している場合、アクセス制御などして誤って消さないよう気を付ける必要があります。
◆クラウドストレージ
物理的な管理が必要なく、どこでもファイルの読み書きができますが、ランニングコストがかかり、従量課金制が多く、容量が多くなれば多くなるほどコストが高くなります。
帳票が多くない会社では、保存方法を決めるだけで良いですが、経理業務に手間がかかっていたり、ペーパーレス化を進めて業務改善を行いたい場合は専用サービスを利用することをお勧めします。
ご案内している資料では、3つの対応方針とサービスについてご紹介しています。
NIKKO
”With” NEWSではオフィスのお役立ち情報を発信しています。