インボイス制度開始まで2か月を切りました。
インボイス制度に対応するためにシステム導入を検討したことはあるでしょうか?
「インボイス制度に対応するには」インボイス制度の仕組みを理解し、制度開始までの期間で対応を行うためにポイントとなる情報をまとめた資料をご紹介します。
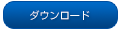 3. 対応するにはどうすればいいの?
3. 対応するにはどうすればいいの?先月の
インボイス制度についてご紹介したメルマガでは、制度開始前に対応すべきことを確認する、簡易的なチェックリストをご紹介しました。
インボイス制度の対応方法を決め、申請作業などを行った後は運用に入ります。
必要な規定事項を記載したインボイスを発行できなくてはなりません。その中では、複数税率を正確に記載する必要があります。
また、インボイスは
電子帳簿保存法の対象書類に該当するので、デジタル化への対応も必要になってきます。
日本・東京商工会議所が2022年9月に公表したデータによると
▶受注業務をデジタル化している事業者売上高1億円以上:約46%
売上高5千万円~1億円以下 :約36%
売上高1千万円~5千万円以下:約19%
売上高1千万円以下:約15%
▶発注業務をデジタル化している事業者
売上高1億円以上:約49%
売上高5千万円~1億円以下:約39%
売上高1千万円~5千万円以下:約26%
売上高1千万円以下:約21%
となっており、いずれも半数を満たしていません。
参考:日本・東京商工会議所「「消費税インボイス制度」と「バックオフィス業務のデジタル化」等に関する実態調査結果」以前「DXの必要性について」メルマガで書かせていただきました。
新たなシステムの導入はコストやリソース面で負担がかかりますが、デジタル化への対応はいずれしていかなければいけません。
インボイス制度の対応を機に、受発注業務のシステム化も検討してみませんか。
インボイス制度、電子帳簿保存法に対応の他にも、
ご要望に応じて最適なシステムをご提案させていただきますので、お気軽にご相談ください。NIKKO
”With” NEWSではオフィスのお役立ち情報を発信しています。